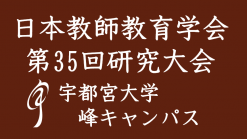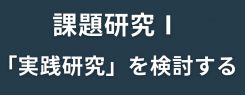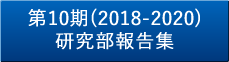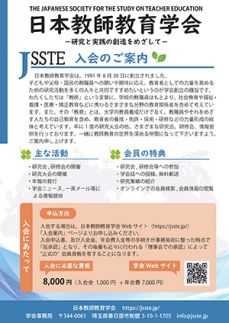査読審査項目別評価基準
2025年1月5日(決定)
2025年9月21日(公開版)
本基準は、日本教師教育学会年報(以下、年報)への投稿原稿の学術的価値と実践的有用性を適切かつ公正に、一貫した評価を行うために、年報編集委員会の内規として定める査読審査基準です。
査読は、以下の項目別評価基準に照らして実施し、それぞれの評価結果を総合的に検討した上で、年報編集委員会の構成員の2/3以上が出席する査読審査判定会議で採否の最終決定を行います。本基準は、透明性を確保し、編集委員会の構成員からなる査読者とそれ以外の査読者(外部査読者)、さらに投稿原稿の執筆者にとって明確かつ公平な審査プロセスの実現を目指して内規として設定しています。なお、本基準は、研究分野の動向や編集方針の変化に応じて、随時見直しを行い、必要に応じて改訂されるものとします。
本基準の適用対象とその活用について
1. 適用範囲
本基準は、年報に投稿された自由投稿原稿すべてに適用されます。
2. 査読者の評価手順
各査読者は、基準に基づいて投稿原稿を評価し、各審査項目の得点および総合得点をエクセルファイルで計算します。その後、得点を『査読結果報告書』に転記し、査読システムにアップロードしてください。
3. 特別な評価視点の取り扱い
審査項目に含まれない視点や、項目を横断する評価がある場合は、それらを『査読結果報告書』に「査読コメント」として記載してください。これらの点については、必要に応じて主査が開催する『査読結果取りまとめ会議』またはチャットで協議の対象にしてください。
4. 最終決定のプロセス
最終的な査読結果は、主査が各投稿原稿の結果を取りまとめ、『査読結果取りまとめ報告書』として作成します。この報告書は編集委員会が参加する「査読判定審査会議」に提出され、議論の上で採否を最終決定します。
審査の各項目について
評価項目:
- 研究の独創性と学術的意義
- 研究・調査方法の適切さ
- 先行研究レビューの適切さ
- 結果の信頼性・妥当性と研究の問いとの整合性
- 論理性と文章表現
- 実践研究としての実践と現場への貢献(実践研究論文・実践ノートに適用)
1.研究の独創性と学術的意義
独創性が乏しく、既存研究との差別化が不十分
- 研究のアイデアや方法が既存のものに強く依存しており、新規性がみられない。
- 学術的貢献の意義が示されていない。
独創性に欠け、新規制はあるが学術的意義が不明確
- 研究にある程度の新規性が認められるが、その独創性は限定的にとどまる。
- 学術的な意義や重要性が明確に示されていない。
独創性と学術的意義が認められる
- 研究の独創性や意義が認められる。
- 既存の研究に対するインパクトがある。
2.研究・調査方法の適切さ
研究・調査方法が不適切で研究目的を満たしていない
- 研究目的や問いに対して選択された方法が不適切である。
- 手法の説明や実施が不十分であり、信頼性や再現性に著しく欠けている。
研究・調査方法が部分的に適切だが、詳細や一貫性に課題がある
- 研究・調査方法が研究・調査の目的にある程度対応しているが、選択理由や実施の詳細が不明確。
- 論理的な一貫性に問題があり、改善が求められる。
研究・調査方法が適切で、研究目的を満たしている
- 研究・調査方法が研究・調査の目的や問いに適合しており、選択理由や実施過程が適切に説明されている。
- 論理的な一貫性が保たれている。
3.先行研究レビューの適切さ
先行研究の選択に偏りがあり、研究との関連性が弱い
- 一部の先行研究のみが取り上げられ、その選択基準が不明確である。
- 既存の知見の整理が不十分で、現在の研究に十分な基盤を提供していない。
先行研究の選択は概ね適切だが、代表性や整理に課題がある
- 主要な先行研究が取り上げられているが、代表性に欠けている。
- 既存の知見との関連性が論理的に十分に説明されていない。
先行研究の選択が適切で、研究との関連性が示されている
- 適切で十分な先行研究を取り上げている。
- 既存の知見の整理と研究との関連性が論理的に示されている。
4.結果の信頼性・妥当性と、結論と研究の問いとの整合性
分析や解釈の結果の信頼性・妥当性が低く、結論も研究の問いとの整合性に欠けている
- 分析や解釈の結果の信頼性が低く、データやテクストの分析や解釈に曖昧さが残る。
- 分析や解釈の結果に照らして妥当な結論が示されていない、または結論が研究の問いとの整合性を欠いている。
結論と研究の問いとの整合性は認められるが、分析や解釈の結果の信頼性・妥当性に課題がある
- 分析や解釈の結果に、一定の信頼性は認められるが、結果の妥当性や解釈に曖昧さが残る。
- 結論は研究の問いに概ね対応しているが、その深度や具体性に不足している。
分析や解釈の結果に信頼性・妥当性があり、結論にも研究の問いとの整合性も認められる
- 分析や解釈の結果に高い信頼性が認められ、データやテクストに基づいた妥当性がある。
- 結論は研究の問いと整合性があり、データやテクストの分析や解釈の結果とも一致している。
5.論理性と文章表現の適切さ
論理構成に一貫性が欠け、一部の文章表現が不適切
- 論理の展開が部分的に不十分で、主張と結論の関係が弱い。
- 文章表現に一部不明瞭な箇所があり、可読性に支障をきたしている。
論理構成と文章表現が概ね適切だが、改善の余地がある
- 論理の展開と結論が全体的に適切だが、一部で曖昧さや論理の飛躍がある。
- 文章は基本的に正確だが、冗長な箇所や表現の洗練が不足している。
論理構成が明確で一貫性があり、文章表現も適切
- 論理の展開が明確で、主張と結論が論理的に結びついている。
- 文章表現は正確かつ簡潔で、全体として高い可読性を維持している。
6.「実践研究」としての実践と現場への貢献(「実践研究」の場合)
実践と現場への貢献が限定的で、具体性に欠ける
- 実践とその現場への貢献が部分的に認められるが、その応用可能性や有効性が不十分。
- 実践とその現場の課題との関連性が弱く、提案が抽象的にとどまる。
実践と現場への貢献があるが、具体性や実用性に課題がある
- 研究成果が実践とその現場に一定の貢献を示すが、提案の具体性や実行可能性の検討が不十分。
- 実践とその現場の課題解決に向けた具体的な方向性がやや不足している。
実践と現場への貢献が明確で、具体性と実用性が十分にある
- 研究成果が実践とその現場の課題解決に有効であり、具体的な提案を示している。
- 実践とその現場のニーズに即した応用可能性を有している。