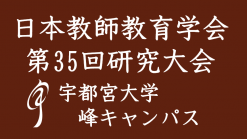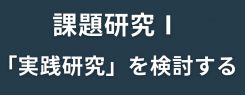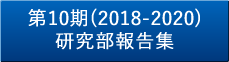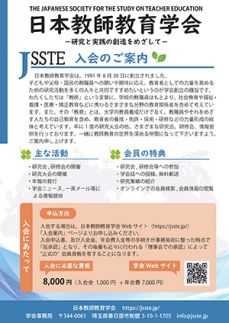査読にあたってのお願い
1.査読の役割とは
査読の目的は、投稿原稿(研究論文・実践研究論文・研究/実践ノート)が、学術的な価値や質を備えているかを確認し、執筆者に建設的なフィードバックを提供することにあります。
投稿原稿の価値を判断するのは査読者の役割ではありません。原稿の社会的・学術的価値を最終的に判断するのは、他の学会員であり、研究者や実践者であり、政策決定者であり、社会であり、読者です。したがって、内容の責任は執筆者(投稿者)に帰すものです。
査読者の役割は、投稿された原稿が基本的な条件を満たすものであるかを基準(ガイドライン)に照らして客観的に判断することです。このことを念頭に、査読者には、教師教育分野での学術的な発展や実践の深化に貢献する可能性のある議論であれば、積極的に採録する方向で審査・評価し、不足する点に具体的で実現可能な改善策を提示する役割が求められます。
2.公平性と客観性の確保に必要な姿勢
査読と査読で記載するコメント(査読コメント)は、指導者による指導助言と全く異なるものです。査読者の個人的な思想や好み、またそれぞれの専門性とその研究手法の偏りを査読の審査に持ち込んではなりません。つまり、「自分の研究スタイル」を押し付けず、執筆者の主張や方法論を尊重する姿勢が大切です。
そのため、自身が査読を担当する投稿原稿が自分の専門知を「大きく」逸脱する場合は、無理に判断するのではなく、速やかに編集委員会に相談してください。
3.加点式の評価と建設的なコメントを心がける
学会誌に掲載する原稿で最も重要なポイントは、その議論や視点の新規性(オリジナリティ)にあります。他の学術領域と同様に、教師教育の領域における研究や実践は、常に新たな知見と可能性にひらかれており、この可能性の前には、査読者がそれぞれに持つ経験も専門的な知見も限られていることを念頭に査読を務めることが求められます。したがって、査読は、「減点方式」ではなく「加点方式」で評価・判定を行う必要があります。
- 査読者の役割は、原稿を「採録可能なレベル」にする最低限の改善点を示すことです。完璧な論文を目指す要求や、過度な改善条件を示すことは、査読者の役割ではありません。
- 論文の強みや良い点を見つけて積極的に評価してください。
- 学術分野の多様性(学際性)を尊重し、執筆者が用いる手法を最大限に活かすことを心がけてください。
- 不足する点などの指摘事項には、合理的で具体的な改善案や提案を用意してください。
- 言葉遣いや指摘は断定的でありながらも丁寧なものを心がけてください。
- コメントは努めて具体的に記載してください(「この部分が不明瞭」といった批判的な指摘に加えて、「何が主語かを改めて明記する」や「こういう視点からの検討が必要」などという具体的な提案を示してください)。
4.執筆者の視点に立つ
執筆者にとっての査読は、研究を改善し学問的に認められるための重要なステップです。過度な修正要求や、不必要な指摘で負担を増やさないように配慮してください。
また、「不適切だ」「役に立たない」「何を言っているのかわからない」といった断定的否定ではなく、「〜といった改善が必要」「ここを強化すると良い」といった支援的な表現を用いるように心がけてください。査読者には同じ領域で研究と学術的な深化に努めるピア(仲間)として、「批判」ではなく、「建設的な批判」が求められていることを常に念頭においてください。ましてや、研究結果が査読者の意見や知識と異なる場合でも、結果そのものを否定しないでください(見解の相違は査読結果に反映させるのではなく、学会誌上での反論や討論として行わなくてはなりません)
5.査読の枠を超えない
査読を担当する投稿原稿には、論文執筆のマナーや文章構成が未熟なものもあります。また、大学院生などの若手研究者・実践者からの投稿も多くあります。ただし、査読の枠を超えることのないように心がけてください。
例えば、論文の書き方を根本から改変させるような指導や、実験の大幅な追加を求めるようなコメントはしないでください。論文の不備を指摘しつつ、それが採録可能なレベルに到達するための最低限の改善点を指摘することが査読(および査読コメント)の役割であることを常に念頭において審査してください。
6.守秘義務を徹底する
査読の依頼を受けた事実や、論文の内容、査読で知り得た情報を第3者に漏らしてはいけません。また、査読で知り得た情報を、人事やその他の目的で使用することも倫理違反にあたります。さらに、査読で知り得た情報を自らの研究に援用したり、無断で使用したりすることは、深刻な研究倫理違反にあたります。
7.迅速な対応
査読は、指定された期間内に必ず完了させなくてはなりません。やむを得ない事情で期限に間に合わない場合は、速やかに編集委員長に連絡し、状況を報告してください。
8.困った時にはすぐ相談
自分の専門外と思われる場合や、意見がまとまらない場合、研究倫理違反や利益相反が考えられる場合には、年報編集委員会にご連絡ください。
最後に
査読は、学術研究を支える重要な役割です。また、経験を積むことで査読スキルも向上します。査読は手間もかかりますし、難しく感じるかもしれませんが、上記の心得を意識して臨むことで、執筆者や学会をはじめ、学術に重要で意義のある貢献ができる得難い機会です。ご協力に感謝申し上げますとともに、最後までどうぞよろしくお願い申し上げます。
2025年1月5日(年報編集委員会)