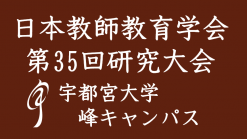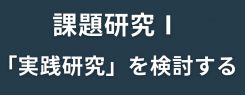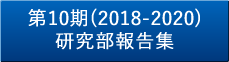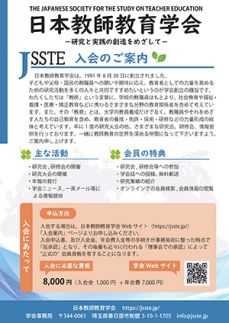投稿原稿中の表記について
(2003年10月3日、年報編集委員会決定)
(2005年9月23日、年報編集委員会決定一部改正)
(2013年9月14日、第62回理事会一部改正)
(2021年9月19日、年報編集委員会一部改正)
(2024年4月20日、第87回理事会一部改正)
1 注および引用文献の表記については、論文末に一括して掲げる形式をとる。注と引用文献の表記と提示の方法については、別途「参考・引用の方法と文献リスト作成のガイドライン」に示す。
2 記述中の外国語の表記について
外国人名、地名等、固有名詞には原語を付ける。外国語の引用文献および参考文献は、原則として原語で示す。また、叙述中の外国語にはなるべく訳語を付ける。外国語(アルファベット)は、大文字・小文字とも半角で記入するものとする。中国語、ハングル等、アルファベット表記以外の文字も、これに準ずる。
参考・引⽤の⽅法と⽂献リスト作成のガイドライン
(2023年2月23日、年報編集委員会決定)
1. 注および引用文献の記載方法は、注方式または引用文献一覧方式のいずれかとする。ただし、注方式の場合は、注を論文の末尾にまとめて記載するとともに、参考文献一覧を付すこと。
2.注方式について
2.1. 論文の本文中で文献等を引用あるいは参照した箇所に注番号を挿入し、論文末に対応する注番号を付して文献等の書誌情報を示す。
2.1.1. 既刊の論文等から直接引用する場合は、引用部を「 」で括り、該当箇所に注を付す。
(例)ローティーは、「学校システムは、その数が増え規模が大きくなるにつれて、より官僚化されていった」と論じる⑴。(ß 「 」の直後、または該当する一文の末に注をつける)
2.1.2. 既刊の論文等から、本文の段組で6行程度を超える分量を直接引用する場合は、引用部を「 」ではなく、インデント(字下げ)で示し、末尾に注を付す。
2.1.3. 既刊の論文等からアイデアを引用する場合、また要約等の言い換えをして示す場合は、該当箇所に注番号を付して示す。この場合、該当箇所を「 」で示す必要はないが、参照した内容がどの部分であるかが明確になるよう、表現方法に留意すること。
(例)学校の数と規模の拡大は、学校システムの官僚化を牽引してきた⑴との指摘がある。
2.2. 本文中の該当箇所に挿入する注番号は、算用数字を用い、論文の冒頭から末尾に向けて、⑴、⑵、⑶…と通し番号で記載する。
2.3. 注番号は、本文のテキストに対して「上付き文字」で示す。
(例)教師は日常の教育実践に統合された持続的な研修機会から効果的な学びを得る⑴。
3. 引用文献一覧方式について
3.1. 論文の本文中で文献等を引用あるいは参照した箇所のそれぞれに、著者名、発行年、参照ページを()でくくって記すとともに、引用あるいは参照文献の書誌情報を論文末に、最初に著者名のアルファベット順(外国語文献)、次に著者名の五十音順(日本語文献)に一括して記す。
3.2. 文中に引用する場合の表記の例は次のとおり:
・文中の場合: UNESCO(2015)によれば、教師の継続的な職能成長機会を〜要件にする。
・文末の場合: 教師の継続的な職能成長機会を〜要件にする(UNESCO 2015)。
3.3. 既刊の論文等から直接引用する場合は、引用部を「 」で括り、著者名と発行年に加えて、引用元のページ番号を記入する。
・文中の場合:Timperley(2011)によると、「システムに係る〜参画主体にする」(4)。
・文末の場合:「システムに係る〜参画主体にする」(Timperley 2011: 4)。
3.4. 既刊の論文等から、本文段組で6行程度を超える分量を直接引用する場合は、引用部を「 」ではなく、インデント(字下げ)で示し、末尾に引用元の文献の著者名、発行年、参照ページを( )に括って記載する。
3.5. 著者が複数の場合は、次に示すように記入する。
・2名の場合: (鈴木・山田 2014)または(Bowles & Gintis 1999)
・3名以上の場合: (鈴木他 2014)または(Bowles, et al. 1999)
3.6. 論考や概念を、複数の論文等から引用する場合は、以下の例に従う:
・異なる著者の文献の場合: (鈴木 2014; 山田 2020)
・同一著者の異なる発行年の文献の場合: (鈴木 2014, 2015, 2016)
・同一著者の同じ発行年の文献の場合: (鈴木 2014a, 2015b)
4. 引用文献一覧(または参考文献一覧)の作成について(以下、「文献リスト」と表記)
4.1. 文献リストは、本文末(注がある場合は、注の後)に、欧文、邦文の順に記載し、欧文はアルファベット順、邦文は五十音順に配列し、まとめて記載する。アクセント符号(é, ø, åなど)は、その字母となるアルファベットに準じる。また、その他の文字(キリル文字やギリシャ文字など)は、それぞれのアルファベット順に従って欧文と邦文の文献リストの間に置く。
4.2. 欧文の場合
4.2.1. 著者が1名の場合、2名の場合、3名以上の場合の表記について
・著者が1名の場合: 例)Hirschman, A. O. (1972).
・著者が2名の場合: 例)Anderson, B., Walker, E. (2011).
・著者が3名以上の場合: 例)Admiraal, W., et al. (2016).
4.2.2. 書籍(初版の場合)
Hirschman, A. O. (1972). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard.
(出版社が大学出版会—University Press—の場合は、大学名以降を省略可。また、Press, Printing, Publishing, Co. Ltd.等についても省略可。)
4.2.3. 書籍(再版の場合)
Freire, P. (1968/2018). The Pedagogy of the Oppressed. Bloomsbury.
(初版年を示し、”/”を挟んで参照・引用した版の出版年を明記する)
4.2.4. 逐次刊行物
Darling-Hammond, L. (1998). Teachers & Teaching: Testing Policy Hypothesis from a National Commission Report. Education Researcher, 27(1): 5-15.
・論文や記事のタイトルは、イタリックにせず、末尾にピリオド(.)を付す。
・掲載誌のタイトルはイタリックで表記し、巻数を( )で括り、号数をその後に示す。
・掲載ページは、巻号数の後に「:(コロン)」をつけて示す。
4.2.5. Web記事・オンライン資料
4.2.5.1. 著者が明確な場合
Meredith, R. (2023). NI Education: School Staff Strike to Cause “Severe Disruption”. BBC News. 2023.11.9. www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-67362864.
・原則として逐次刊行物に準じ、掲載誌にあたる箇所にサイト名を示す。
・サイト名の後に、公開日を記入。公開日がわからない場合は、n.d.(”no date”を表す)と記載する。
4.2.5.2. 著者がわからない場合
Detailed.com (n.d.). The 50 Best Education Blogs. detailed.com/education-blogs.
・サイトの所有者および管理者(または組織)がわかる場合は、その名前・組織名を記載する。
・サイトの所有者および管理者(または組織)もわからない場合は、サイトのドメイン(例ではdetailed.com)を記載する。
・参照・引用元はサイト全体となるため、発行年には、n.d.(”no date”を表す)と記載する。
4.2.5.3. 行政文書や法律(外国)
USDOE (U.S. Department of Education) (2023). State General Supervision Responsibilities under Parts B & C of the IDEA (OSEP QA 23-01). 2023.7.24. Office of Special Education & Rehabilitative Services. sites.ed.gov/idea/idea-files/guidance-on-state-general-supervision-responsibilities-under-parts-b-and-c-of-the-idea-july-24-2023/
・著者名に文書の責任主体を記入。本文で略称表記した場合には、略称を示し、括弧内に正式名称を記入(事例では、U.S.は略称のままであるが、一般に容易に理解できるものは字数制限の観点から略称のまま記載)。
・文書名・法律の名称を、書誌名に代えて記載する。法律等の記号番号があるものは、文書名の後に括弧付で記号番号を記入し、続けて交付日を記入する。
・文書を発出した組織や責任機関の下部(内部)部局等までを明記するか否かは、執筆者の判断による。
4.3. 邦文の場合
邦文の文献を表記する場合、欧文の文献の表記との大きな違いは、下記の通り:
・著者名は、氏名の全てを記載し、氏と名の間にスペースを開けない。
・著者名に続いて記載する発行年は、全角の括弧に収め、ピリオド(. )は付さない。
・書名は『 』で括って示し、論文・記事のタイトルは「 」で括って表し、括弧の前後にスペースを置かない。
・最後はピリオド(. )ではなく、句点(。)を用いる。
4.3.1. 書籍
牛渡淳・牛渡亮(2022)『教師教育におけるスタンダード政策の再検討:社会的公正、多様性、自主性の視点から』東信堂。
・副題については、「―」が用いられている場合でも「:」で繋ぐ。また、副題の末尾に付された「―」は省略する。
4.3.2. 翻訳書の場合
ダン・ローティー(1975/2021)『スクールティーチャー:教職の社会学的考察』佐藤学監訳、学文社。
・なお、論文の本文中で翻訳書を引用する場合は、①初刊年表記、②実際に参照した版の出版年表記、③両方併記 à例、(ローティー 1975/2021)の何れかを選択し、本文中一貫して用いる。
4.3.3. 逐次刊行物
子安潤(2017)「教育委員会による教員指標の『スタンダード化』の問題」『日本教師教育学会年報』26: 28-45。
4.3.4. Web記事・オンライン資料
欧文の場合と同じ。
4.3.5. 行政文書や法律(国内)
中央教育審議会(2023)「『教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)』(令和5年8月28日中央教育審議会初等中等教育分科会質の高い教師の確保特別部会)を踏まえた取組の徹底等について(通知)」文部科学省(2023.9.8.)www.mext.go.jp/content/230914-mext_zaimu-000031836_1.pdf
・外国の行政文書・法律を記載する場合との大きな違いは、著者名に文書の大枠の責任主体(上記の例では文部科学省)ではなく、文書を発出した部局等(上記の例では中央教育審議会)を示す点にある。
5. 上記に記載のない文献等の参照・引用に際して、本文中での参照・引用の方法および文献リストの作成方法に疑問がある場合は、年報編集委員会(journal@jsste.jp)に問い合わせるか、投稿原稿の該当部分を「緑字」にして示すこと。